1997年 介護保険法成立
2000年 介護保険法施行
1996年に祖父が天国へ召されるその少し前から、祖母の認知機能低下がアップデートを繰り返し、性格や行動もモデルチェンジをし始めた。いつもと変わらない祖母。あれあれ?と、首をかしげざるを得ない何かが見受けられる時がある祖母。
あちら側とこちら側を行ったり来たりする祖母。それでも普通(以前と変わらず)に家族全員笑って暮らしていた。
その時、まだ「認知症」がなんなのか「認知症介護」というやつがどういうものなのか、まったく理解していなかった私達家族。そんな状態の中、みんなで西暦2000年に突入した。
2000年がやってきた
2000年 介護保険法施行
何だかわからない制度が舞い降りてきた。その名は「介護保険制度」なり。「社会全体で介護を支えましょうね♡」と設立された公的で有難い制度だ。家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に創設された介護保険制度。制度が始まって24年経つんですね。
介護保険制度は懐かしい過去…と、祖母にまつわる思い出にしてしまっていたがとんでもない。2024年のいま、今度は母親のために申請の準備をしている最中。終わらない私のviva!在宅介護。
で、24年を遡って祖母の話に戻りますが、その何だかわからない制度「介護保険制度」の世界に飛び込むため、祖母は色んな関門を通過する儀式に挑んた。
脳神経外科でMRIにチャレンジ。CTにもトライ。でも、その機械が何たるかわからない祖母にはどちらの検査も拷問でしかなかった。叫びに叫びまくり、動きに動き回った結果…


画像取るの無理です!でも痴呆は進んでると思います!
医者、お手上げ。
2000年の祖母の脳みそ。もし鮮明な画像に写しだされていたならば、一体どういう診断を下されていたのだろう。まだ、医者の口から「痴呆」という言葉がスラスラと発せられていた2000年のある日。
画像解明が出来ない祖母の脳みそは、とりあえず脳外科医の経験と感覚で「たぶん痴呆」という診断を下され、次の関門「改定長谷川式簡易知能評価スケール」を受けに行くことになった。
祖母・母・孫の3人でいざ出発だ。
改訂長谷川式簡易知能評価スケール
介護認定制度で私の祖母はどう判断下されるのか。そのカギを握っていると言っても過言ではない「改定長谷川式簡易知能評価スケール」(1974年に公表された認知症の診断指標。1991年に改訂されたので“改定”がついてます)の素晴らしすぎる回答で、私は祖母がますます大好きになった。
「長谷川式認知症スケール」は、一般の高齢者の中から認知症の高齢者をスクリーニングすることを目的に用いられる簡易的な認知機能テストです。記憶を中心とした大まかな認知機能障害の有無を調べます。1974年に聖マリアンナ医科大学・神経精神科教授だった長谷川和夫氏らによって開発され、今では認知症の診断にあたって信頼性の高い評価方法として、日本国内の多くの医療機関で使用されています。
1974年の開発当初は「長谷川式簡易知能評価スケール」の名称でしたが、1991年に質問項目と採点基準の見直しが行われ、「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」に改訂されました。また、2004年に疾患名が「痴呆症」から「認知症」に変更されたことにより、「長谷川式認知症スケール(HDS-R)」と呼ばれるようになっています。
HDS-Rとは、開発者である長谷川和夫氏の名前を含めた「Hasegawa Dementia Scale-Revised」の略症です。
SOMPO笑顔倶楽部より引用
2000年のある日。まだ介護認定をする側も介護認定をされる側も、双方経験値が乏しかった記憶がある。介護保険制度が出来たてほやほやという事は、その制度を提供してくれる人達もそこそこ手探り状態。
それなりに福祉の道を歩んできているはずのみなさん。それでも(私が住まう街のみなさんは)新制度についていくのに一生懸命感が隠せない。
そんな
- 医者(結構なおじいちゃん風味)
- 看護師(おじいちゃん先生の付き添い感満載)
- 介護スタッフ(一番しっかりしてそうだけど権限なさそう)
の3人が、私達家族を満面の笑みで出迎えてくれた。私の祖母を子猫かなんかと勘違いしている瞳の医療従事者たち。まあ私もこの時、まだ祖母のMAX底力を知らなかった。
「改定長谷川式簡易知能評価スケール」検査に挑まされた祖母は、私の想像をカンタンに超した。
検査について行ってよかった。楽しかった。それが孫の感想です。
「わからない」をいわない祖母の回避力
その当時の「あらあらおばあちゃんボケちゃて…」の一般論は、(私見ですが)本当に「言動も行動もおかしくなっちゃったわねー…」のような感じが浮かんでくるのでは?
私も、自分の祖母が認知症になるまでは、そんなざっくりとした「周囲と意思疎通が出来なくなる人」イメージしかなかった。
だが、しかし…
うちの祖母は、そんな孫のイメージをガンガンに破壊しながら、煌めく我が道を進んでいった。そんな祖母の我が道を行くパワーに巻き込まれ、祖母の「改定長谷川式簡易知能評価スケール」検査を担当したお陰で、傷を負ってしまった3人の医療従事者たち。
以下、そのやり取り。素晴らしきかなノンフィクション。

お年はいくつですか?

83さいですっ!

100から7を引いたらいくつになりますか?

93です!
まだ和やかな雰囲気。その部屋にいた全員、ああ滞りなく「改定長谷川式簡易知能評価スケール」検査は終わっていくみたいねと思っていた。
医療従事者たちは「よしよし実績積めてるぅ♪経験値上ってるぅ♪」と、子猫のような老婦人で質問のお稽古ができて満足げ。
私は「こんな質問でいったい何がわかるのかなぁ…」と、そのやり取りを見つめていた。

今日はどこに来たかわかりますか?

それは私が答えると失礼にあたるので娘に答えさせます。○○ちゃん(私の母)、あなたから答えてあげて!

わ、わたしがこれから言う言葉を復唱してくださいっ!
桜・ネコ・電車

ええっ?なんでそんないやらしい言葉を私が言わなくちゃいけないんですかっ!😡いやだぁ!!こんなところで言えるわけないじゃない!信じられない、あーいやだ!😡😡
孫のドキドキワクワクが始まった瞬間。この「改定長谷川式簡易知能評価スケール」というやつ。一体何のためになるのやら…という私のクエスチョンは吹っ飛び、と同時に腹筋が崩壊し始めた。

まだすべての質問が終わっているわけではなさそう。おじいちゃん先生、必死で頑張っているご様子。

わ、わ、わたしがこれから言う数字を逆から言ってみてもらえますか?

あらぁ、もうちょっと早く言ってくれれば言えたんですけどねぇ・・今言われてもちょっと無理ですねー。今それを言う時間じゃないですから♪

ええと(半ベソ)・・・じゃあ、これからお見せするものを覚えてくださいね。それを隠しますので、何があったか思い出して答えて下さい(半ベソ)

別に答えるのは構いませんけど・・・でも、それが一体何の意味になるんですか?なんでそんなに色々答えさせたいんですか?

どうやっても「わからない」という言葉を言わない祖母。
祖母は「改定長谷川式簡易知能評価スケール」を質問返し手法でぶっ潰しまくった。

し、しっている野菜の名前をできるだけ沢山言ってもらえますか?
顔、半ベソ。ココロはきっと大号泣な医者に笑顔で返す祖母。

野菜ねぇ・・もちろん沢山知ってますよぉ。でもひとさまにお伝えするほどの事ではありませから。ちなみにあなただったらどんな野菜を言いますか?ちょっと言ってもらっていいですかぁ?
燃え尽きて灰になった医者
アゴが外れたような顔した看護師
憂いながらうつむいた介護スタッフ
そんな3人の気持ちなんぞ知る由もない私の祖母。小さくてかわいい私のばあちゃんは、おじいさん先生を粉々にしてしまった。
孫、とても楽しかった
「さあ帰りましょ♡」と、苦笑いの母と腹筋が崩壊した孫を引き連れ祖母帰宅。
自分が今日何のためにどこへ連れていかれたのか理解しないまま、祖母は認知症になるための準備を終えた。
認知症の準備完了
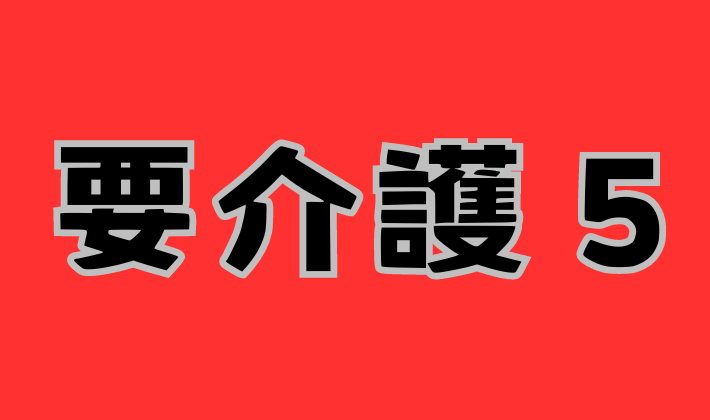
頂きました「要介護 5」
いきなりてっぺんとった祖母。介護サービスを受けたくはあるものの、私の祖母はそんなにひどい状態なのか?と、自分勝手に悲しくなった。
で、要介護認定の基準とは?
要介護度は、「自立」「要支援1・2」「要介護1~5」の8つに区分されており、要介護認定を受けることで、ご本人の身体や精神の状態に応じてそのいずれかに判定されます。以下、それぞれがどのような状態にあるのか説明します。
自立(非該当)
歩行や起き上がりなど、日常生活上の基本的な動作を自分で行うことが可能で、かつ、薬の服用、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態です。
要支援1
食事や排泄、入浴などの基本的な日常生活動作は自立していますが、起き上がりや立ち上がりの能力などが低下している状態です。また、手段的日常生活動作(電話、食事の支度、買い物など)の一部で見守りが必要な状態です。
要支援2
要支援1よりも、歩行や立ち上がりで介護者の見守りが必要な状態です。ただし、病気・障がいの有無によっては要介護状態となりえます。
要介護1
要支援2よりも、起き上がり・立ち上がりの能力が低下している状態です。片足での立位や一人での買い物が難しくなり、部分的な介助が必要となります。
要介護2
入浴時に身体を洗うことや歩行など日常生活において、一部の介助が必要となる状態です。手段的日常生活動作では、自立した金銭管理や食事の支度が難しくなります。人によっては認知症の症状が出て、日常生活上のトラブルに発展する恐れがあります。
要介護3
要介護2よりも認知機能(理解、判断、論理的思考など)や身体機能が低下している状態です。ご自身での寝返り、トイレ、歯磨き、更衣が難しく、全面的な介助が必要です。また、自立歩行が困難で、状態によっては杖や歩行器、車いすなどの福祉用具が必要となります。
要介護4
日常生活の多くの場面で、要介護3以上に介助が必要な状態です。自力での移乗、移動、洗顔、整髪が難しく、介助が必要となります。また、座位を保持すること、両足で立つことが困難で、移動には車いすが必須となる場合が多いです。加えて、認知機能の低下が著しく、日常生活を送るうえでは常時介助を要します。
要介護5
生活のあらゆる場面で常時介護が必要な状態です。重度の認知症や身体上の麻痺があり、日中はほぼ寝たきりの状態となり、日常生活のすべてにおいて介護者による介助が不可欠となります。
介護サービス情報サイト「SOMPOケア」より引用
介護サービスを受けたいと願っているものの、よそ様から「ガッツリ認知症ですよ!」と太鼓判押されると、何だかそれはそれで切ない感じがするのね。まだ「介護者」としての認識が薄かった私達家族。勝手なもんだ。
でも「まじ⁈要介護5⁈」みたいな変なテンションが家中に溢れかえったのも事実で、ばあちゃんでかした!と、ありがたくサポートを受けることにした。
この介護認定を受ける事から、本格的な「認知症患者」としての祖母の生活がスタートした。ただ漫然と日々を送らず、認知症の家族と楽しく暮らす事とその進行を出来るだけ抑える事。
そして穏やかな毎日を皆が送ることが出来るように、私達家族は考えながら生きてゆかなければならなくなった。そんな私達の決意を知らない祖母。
「今日はどこに行ったんだっけ?」
そう問いかけても「わかりませーん♡」とニコニコしながらどら焼きを頬張る祖母。本日初めて「わからない」を言った。
そとヅラだけはいっちょ前。
2024年も介護認定の準備は続く
祖母の介護生活を終えて20年以上経過した2024年4月。今は私の母の介護認定申請をしている最中。「申請は通ると思うけど支援か要介護のどちらになるか難しいところ…」と、地域包括支援センターの方に言われた。とりあえず申請が通るのならそれでよし。母娘でそう思いながら、面接が終わった後にどら焼きを食す。
どれだけ時間が流れようとも、面接後のおやつ。我が家はどら焼き。
そしてどこまでも続く私のviva!在宅介護。さらに20年前の縁も続く。祖母の介護を担当してくれた人が、母の介護申請のため、再び我が家にやってきた。
離職率高いと聞いているこの業界で、まさか親子二代にわたって世話されるとは思ってもみなかった。
在宅介護を頑張る家族に幸あれと、自分とどこかの誰かに言う。
この祖母のお陰で、今の私はアルツハイマー型認知症の父となんとか暮らしていけている。
在宅介護を頑張る家族に幸あれと、自分とどこかの誰かに言う。
頑張らずに頑張れと、自分とどこかの誰かに言い聞かせる。

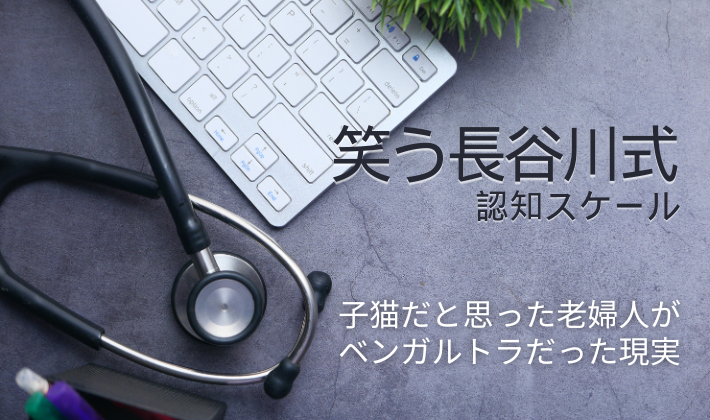



コメント